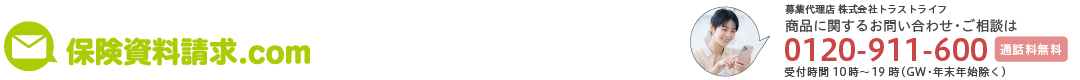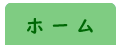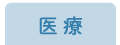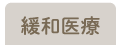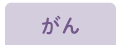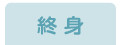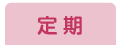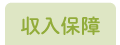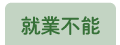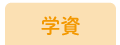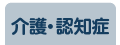今回は、出産を控えているご家庭でぜひ確認していただきたい『育児休業給付金』についてです。
長期間にわたって収入がなくなる育休中の給付金ですので、しっかり理解しておきたいところ!
「私ももらえるのかな?」
「すぐに受け取れるのかな?」
そんな疑問を解決していきます。
この機会に制度の内容や条件、受けられる給付金額などをご確認ください!
育児休業給付金の概要

会社に勤めていた人が育児のため休業するときに受け取れるのが“育児休業給付金”です。
この給付金は、1歳から最長2歳までの子どもを育てるために休みを取った場合が対象となり、
雇用保険の被保険者であれば男女問わず受け取れる給付金です。
出産手当金のように女性のみではないのが嬉しいポイントです。
受給資格があるのはどんな人?
ただし、雇用保険に加入していれば全員誰でも対象、というわけではないので注意は必要です。
具体的には、以下のような条件をクリアしている必要がありますので事前に確認をしておきましょう。
①休業開始前の2年間に、給与が発生する日が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること
②育児休業期間中の各1ヶ月に、休業開始前のお給料8割以上の賃金の支払いを受けていないこと
③就業している日数が支給単位期間ごとに10日以下、もしくは80時間以下であること
少しややこしい部分もありますね。
勘違いしやすいところ、よくわからない言葉の部分を補足します。
1ヶ月の考え方
受給資格の要件になっていたり、支払単位期間になっていたりする1ヶ月の考え方はしっかり覚えておきましょう。
基本的にこの時言う1ヶ月というのは、育休に入る日からさかのぼっての1ヶ月です。
つまり育休に入るのが11/20だった場合は、
1ヶ月は、10/20~11/19、9/20~10/19、8/20~9/19・・・となります。
①の受給資格を解説
では、『①休業開始前の2年間に、給与が発生する日が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること』を具体的に考えてみましょう。
1ヶ月の考え方を踏まえたうえでお給料が発生する日が11日以上というのはわかりやすいと思います。
10/20~11/19、9/20~10/19、8/20~9/19のそれぞれの1ヶ月に、
お給料が発生する日が11日以上あればいいわけです。
普通に出勤して仕事をした日は当然のこと、有給を使用した日もこの日数に含めます。
では次に気になるのは“完全月”という、あまり聞きなれない言葉です。
これは、1ヶ月丸々ある月のことをさす言葉。
先ほどの1ヶ月の考え方もあわせて育休に入るのが11/20だった場合は、
10/20~11/19、9/20~10/19、8/20~9/19は完全月ですが、
9/1~9/19は完全月とは言えません。
その為、もし仕事について1年たつか経たないか・・・という段階での妊娠出産の場合は、
自分は対象になるのかどうか、事前にきちんと確認をしてみましょう。
受取れる金額は?

給付金額は育休の時期によって2段階に分かれます。
育休開始後180日以前 … 1日当たり = 休業開始時賃金日額 × 67%
育休開始後180日以降 … 1日当たり = 休業開始時賃金日額 × 50%
※休業開始時賃金日額は、直近で仕事をしていた6ヶ月間の賃金合計額を180で割った額。
※1ヶ月は30日で計算。
額面給与30万円で計算
たとえば額面給与が30万円だった人は、
育休の前半と後半でもらえる1日当たりの金額の計算はこのようになります。
休業開始時賃金日額 ・・・ 30万円 ÷ 30日 = 1万円
育休開始後180日まで1日当たり ・・・ 1万円 × 67% = 6,700円
育休開始後180日以降1日当たり ・・・ 1万円 × 50% = 5,000円
もらえる額の目安をざっくり紹介
計算するのが面倒・・・という方のために、ざっくりとした目安だけちょっとご紹介です。
できればご自身でも計算するのがいいとおもいますが、簡単に確認したい方は参考までにご確認ください。
【平均月額15万程度】
育休開始後180日以前・・・月額10万円程度
育休開始後180日以降・・・月額7,5万円程度
【平均月額20万程度】
育休開始後180日以前・・・月額13,4万円程度
育休開始後180日以降・・・月額10万円程度
【平均月額30万程度】
育休開始後180日以前・・・月額20,1万円程度
育休開始後180日以降・・・月額15万円程度
支給額には上限がある
ちなみに、育児休業給付金には上限があります。
念のため上限をチェックしておきましょう!
2021年3月現在ではこちらの金額になりますが、
この金額は毎年8月1日に変更されるので注意してみてください。
【上限額】
67%支給時・・・月30万5,721円
50%支給時・・・月22万8,150円
受け取れる期間は?
育児休業給付金は、原則子どもが1歳に達する日前まで取得した育休に対して支給されます。
ただし、やむを得ない状況の場合、子どもが1歳6ヶ月になるまで延長でき、
さらにやむを得ない状況が続いた場合は2歳に達する日まで延長することができます!
2歳まで延長できるようになったのは平成29年の10月1日から。
それまでは、最長で1歳6ヶ月までの延長でした。
どうしてもキビシイ・・!というときには、少し安心できる改正ですね!
ただし、いきなり2歳まで延長できるわけではなく、あくまで1歳6ヶ月までの延長をした後の再延長です。
段階を踏まなければいけないので、そこは覚えておきましょう。
やむを得ない状況とは?
あわせて覚えておきたいのは、1歳6ヶ月まで、そして2歳まで延長するためには条件があるということ。
あくまで、やむを得ない状況の場合と認められた場合のみなので、注意が必要です。
具体的にいうと、次の2つのどちらかに該当した場合となります。
①保育施設に入れなかった場合
保育所への入所を希望し申込みを行ったが、落ちてしまって入れなかった場合。
(申込自体していなかった場合は対象になりませんのでご注意ください)
②配偶者が養育できなくなった場合
育休をとっていた人の配偶者が死亡、病気、障害状態になり、育休明けに配偶者が養育できなくなった場合。
また、離別により配偶者が養育できなくなった場合。
(この場合の配偶者は、法律婚の関係になくとも、事実上婚姻関係と同様である方も含まれます)
2番目の方が少しわかりづらいと思うのですが、イメージとしては、
『自分の育休明けには配偶者が子供の面倒を見てくれるはずだったのに、頼れなくなってしまった!』という場合です。
残念ながら、育休をとっていた本人が『病気、障害状態になり養育できなくなった場合』は延長の対象にはなりません。
あくまで、この延長の体調になるのは育休をとった人の配偶者に何かがあった場合なので注意しましょう。
支給のスケジュールは?

支給される金額と期間がわかれば、あと気になるのは“いつ受け取れるのか?”ですよね。
育児休業給付金は、原則育休に入って2ヶ月後から支給が始まります!
出産したお母さんが受け取る場合は、
出産後約2ヶ月は産休をとり、そこから育休に入って2ヶ月後に支給されるので、
出産から考えると約4ヶ月後からの支給です。
それ以降は原則2ヶ月に1度のペースで申請を行い、支給を受けるようになります。
また、受け取る本人が希望する場合は申請を1ヶ月毎行い、
毎月育児休業給付金を受け取ることも制度上は可能です。
気になる方は会社の担当部署に確認してみてください!
手続き方法

概要も分かった、金額の目安もついた!となると、最後に気になるのは、手続きの方法。
先ほど原則2ヶ月に1度申請をするとご紹介もしましたし、あんまり大変な手続きだと、
給付金がもらえるのはわかっても気が重くなってしまいますよね。
ですが、ここもあまりハードルは高くないので安心してください!
基本的には、申請書は勤務先から提出するのが一般的です。
手続きの流れとしては、下記のようになります。
(自分でやること)勤務先に育休をとりたいことと、いつまで取る予定であるというおおよその期間を伝えておく。Step1
勤務先がハローワークに書類を提出し、受給資格確認手続きを行う。
受給資格が確認できた場合、“育児休業給付金支給申請書”が勤務先に交付される。Step2
勤務先から申請書が渡される。
(自分がやること)書類に記入、押印をして勤務先に提出。
Step3
勤務先がその後の手続きを行い、申請してから(出産してから)約4ヶ月~5ヶ月後から支給開始。
その後、2ヶ月毎(希望によっては1ヶ月毎)の申請も、勤務先が行う。
自分で手続きをすることも可能
また、基本的には勤務先から提出するのが一般的ではありますが、
要望であれば自分自身で育児休業給付金の手続きも可能です。
ただし、そうすると初回申請も、2ヶ月毎(希望によっては1ヶ月毎)の申請も、
当然ながら自分で行わなければなりません。
もしも期限内に手続きを済ませるのを忘れてしまった場合は、
育児休業給付金は受け取れなくなりますので注意が必要です。
ハローワーク側も原則は勤務先からの手続きを推奨しているようなので、
よほどのことがない限り手続きは勤務先に任せたほうがよさそうです。
まとめ
今回は育児休業給付金についてご紹介をしました。
最後に改めてポイントをまとめておきます!
☆受け取れる金額は2段階
・育休開始後180日以前 … 1日当たり = 休業開始時賃金日額 × 67%
・育休開始後180日以降 … 1日当たり = 休業開始時賃金日額 × 50%
☆受け取れる期間は原則子どもが1歳になる前日まで、状況に応じて最大で2歳になる前日まで延長可能
☆支給タイミングは滞りなく手続きを行って出産から約4ヶ月後
☆支給は原則2ヶ月毎申請し、支給。要望によって1ヶ月毎の申請も可能
☆手続きがスムーズに行えるよう、産休前に会社に育休取得を申し出て手続きについて確認しておく
最長2歳まで取れるようになった育児休業給付金。
ただ、ありがたい制度ではありますが実際の収入は以前の2/3、1/2になりはしますので、
受け取れる額をしっかり把握して、金銭的に慌てなくて済むようにしておきたいですね。
ぜひ余裕をもって行動できるよう、確認をしておいていただければと思います!
また出産を控えている方の場合は、これ以外の出産にまつわる公的制度なども踏まえたうえで直近のお金の流れ、また今後の家庭のライフプランも考えていく必要が出てきます。
よろしければ弊社のサービスで、お金のこと、ライフプランのこと、保険による解決方法などを無料でご相談いただけるサービスもあります!
ご興味がありましたら是非こちらも確認されてみてください。