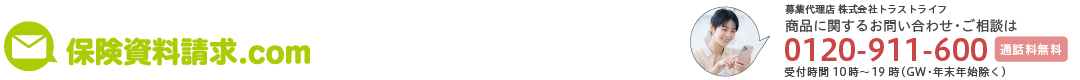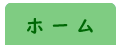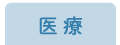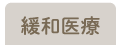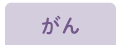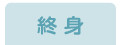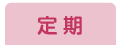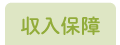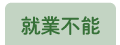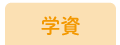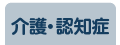今回お伝えするのは、保険金・給付金の請求期限についてです。
せっかくいざという時の為に準備している保険ですから、何かあった時にはしっかり活用したいところ。
ただ、中には請求しないまま時間が経過してしまって・・・なんてこともあり得ます。
本当は受け取れるはずだったのに請求期限切れで権利が消滅、なんてなるともったいないですよね。
そこで今回は、請求に期限はあるのか?あるならどの位なのか?について基本的な内容をご説明していきたいと思います!
結論だけ知りたい方へ!
『請求期限は“ある”!原則のルールとしては3年間。超過している場合は保険会社に確認を』
結論はご確認頂いた通りなのですが、そもそもそんな請求漏れなんかする?というところや、原則のルールは全保険会社で共通なのか?なぜそう言えるのか?という事について少しご説明していこうと思います。
くわえて、こんな方。
💡給付金請求漏れはないですか?
「簡単な #手術 だから対象じゃないでしょ」
「一泊しないで帰ってきたから #入院 じゃないでしょ」
という方が、結構います。でもちょっと待って!#保険 によっては、保障される可能性もあります!
些細な事でも問い合わせてみましょう☝️— 保険資料請求.com (@hoken_siryo) June 4, 2020
「結構前に入院・手術をしたけど、まだ請求できるかな?」という方にご確認いただきたいのはもちろんですが、自分が保険に加入している、家族が保険に加入しているという場合は『全く関係ない』とは言えない内容となりますので、今後のためにもぜひご確認下さい!
また、保険自体を新たに検討中でプロに相談をしてみたい・・・というかたはこちらへ。
→自分に合った解決方法をプロに相談したいなら、無料で何度でも相談できる保険無料相談.com
どんな商品があるのか、資料を確認したいという方はこちらへどうぞ。
なんで請求漏れが起きるの?

前提として、保険会社は保障の対象になる1人1人の入院や手術などの状況を逐一把握する方法はなく、契約者からの保険金・給付金請求でしか支払い事由が発生したことがわかりません。
「支払い対象なので請求してください」といった案内ができない以上は、請求する・しないというのは契約者の認識次第です。
そうすると「入院手術をしたのに請求しないなんてことある?」と疑問に思うかもしれませんが、例としてはこんなパターンがあります。
簡単に内容をご紹介するので、こんなところに注意すればいいのか、と確認してみて下さい。
日帰り入院で入院の認識がなかった場合
病院に行ってその日のうちに帰ってきた・・・という時は通院の範疇だと思いがちですが、実は日帰り入院だった、という場合があります。
自分で判断するのは難しいかもしれませんが、窓口での支払い時に受け取る領収書を確認して、『入院料等』というところに点数が書いてあれば、それは通院ではなくて入院の範囲です。
ただ、あまりまじまじと領収書を見るという方も多くないと考えられるため、請求しそびれた、ということも起こりうるわけです。
まずは請求漏れを起こさないためにも、病院にかかった時には請求書を確認するようにする癖をつけてみましょう。
ただし、そもそも日帰り入院の保障がない保険に加入していた場合は対象になりませんし、また実際に請求したとしても支払いに関しては保険会社の判断になります。
必ず支払われるわけではないことはご注意ください。
日帰り手術で手術の認識がなかった場合

入院と同じように、病院に1泊もせずに終わる簡単に思える治療を受けたとき、単なる処置だと思っていたら実は手術だった、という場合もあり得ます。
これも判断基準は入院と同じく領収書です。『手術』というところに点数が書いてあるかどうかで手術扱いかどうかを判別することができます。
ただ、保険商品によって保障の対象になる手術は明確に決められており、これも手術だったからと言って必ず支払われるわけではありません。
あくまで、加入保険の対象であるかどうか、保険会社の判断次第であるという点はご注意ください。
対象の方の加入保険を把握していなかった場合
これは加入している保険について、家族に伝えていなかった場合に起こり得るケースです。
家族が知らなければ当然請求しようとも思いませんので、既加入保険を家族に伝える機会がないまま突然の事故で・・・といった場合等に請求漏れを起こす可能性があります。
加入している保険があるかわからない時や、知っている以外にも何か加入している保険がないか確認したい時は、通帳やクレジットカードの明細などを確認すれば、保険料の支払い履歴から推測することができます。
ただ、もし一時払いや全期前納などで最初に全て保険料を支払っている場合は保険証券でも出てこない限りは気づきづらいので、当然ではありますが加入保険については家族にしっかり共有しておき、請求漏れを防ぐことが必要です。
保障内容を正しく理解していなかった場合
入りっぱなしで内容はあまり覚えていない・・・という方で起こりやすいのがこちら。
主契約と言われる、保険のメインと言える保障部分については覚えていても、細かい特約の内容までは把握していないというケースは少なくありません。
そうすると、『万一の時にしか使えないと思っていたら、実は特約で医療保障がついていたことに随分経ってから気づいた』なんてこともあり得ます。
ぜひ、ご自身の加入内容に関しては保険証券を見てしっかり確認をしておきましょう。
レアケース:加入したばかりの場合
最後、これはレアケースではありますが、対象かも、と思いながら請求していなかったという方もいらっしゃいます。
面倒だった、やんなきゃと思っていてそのままという場合もありますが、意外なのが『加入したばかりだったから』というもの。
お客様の声を聞いていく中で「入ったばっかりで保険料もそんなに払っているわけではないのに請求するのは申し訳なくって・・・」という理由で請求していない方がいらっしゃることに驚いたことがあります。
こればかりは、そういう時のための保険なわけなので、むしろ「このタイミングで加入してよかった!」としっかり請求していただきたいです!
請求したからと言って保障内容が変わるわけでも、保険料が変わるわけでも、対応が変わるわけでもないのでご安心下さい。
保険の請求期限は?

さて、ここまではなぜ請求漏れが起こってしまうのか、という内容についてご紹介をしてみました。次はいよいよ本題の保険金・給付金の請求に期限についてです!
・・・とは言っても、結論はすでに冒頭でご紹介していますので、請求期限があるという事はもうご承知の通り。冒頭での内容の復習になりますが、請求期限は3年と定められています。
これは保険会社に裁量で設定しているルールなのか?など、少し細かいところを確認してみましょう。
期限の根拠日帰り入院で入院の認識がなかった場合
まずこの3年間という請求期限についてです。
これは保険会社が各々個別で決めているわけではなく、保険法で定められている内容です。
そもそも保険法とは何かというと、保険契約はどのように成立するのか、効力を持つのか・・・等について定めている日本の法律。
そのため、基本的にはどの保険会社の保険に加入していても、この保険法の影響を受けることになります。
請求期限について書かれている部分を、保険法原文のままご紹介するとこんな感じです。
第九十五条
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
出典:e-Govウェブサイト
前半の言葉が難しいので少しややこしく見えますが、要は『請求する権利は3年間使わなければ時効で消滅』という事です。
では、保険法で定まっている通り3年経過で権利が消滅してしまうとなると、それ以降は絶対に保険給付は受けられないのでしょうか?
3年を超えたら絶対に受け取れない?
実はこれに関しては、保険会社や請求する内容などによって判断が分かれるところとなります。
保険法で定められているのは、権利が消滅する、という事だけ。「保険会社はそれ以降請求を受けても、一切受け付けてはならない」とは定めていません。
そのため、実際に支払い対象になるかどうかというのは別ですが、保険会社によっては『万が一、3年以上過ぎている場合にはお問い合わせください』とオフィシャルサイトに記載しているところもあります。
支払いの対象になるかどうかは、提出した書類をもとにした保険会社の判断次第。無事支払われる場合もありますので、まずは請求漏れに気づいた場合は保険会社に問い合わせを行いましょう!
ただ当然ですが、必要な書類が揃えられなければ請求には応じてもらえませんし、あまりにも時間が経過しすぎている場合も難しい可能性が高いようですので、そこは念頭に置いておいていただければと思います。
請求時に必要なもの
ここまでで、保険給付の請求期限についてご説明しましたが、最後に補足として必要書類についても簡単にだけご紹介したいと思います。
保険会社から送られてくるもの、自分で用意するものとありますので、この機会に少し確認してみてください。
ちなみに、ここでご紹介した書類はあくまで一般的に必要になる書面であり、保険会社や請求する給付金やその詳細によっては異なる場合もありますのでご了承ください。
もちろん実際に請求するときには保険会社からもキチンと必要書類の案内がありますので、いざ請求するとなった時はそちらをご確認しながら準備をすすめましょう。
死亡されたときの生命保険金請求
まずは無くなった場合の保険金請求の場合についてみてみましょう。
死亡時に必要になる書面は、一般的にはこういったものになります。
死亡保険金請求書(保険会社から送付)
事故状況報告書※事故の場合(保険会社から送付)
死亡診断書
亡くなったことが確認できる住民票
受取人の本人確認書
受取人の戸籍謄本が必要だったりする場合もあり、生命保険金の受け取りの提出書類は種類が多くなります。
コピーの提出でよいもの、会社所定の書式でなければならないもの等もありますので、まずは保険会社から送られてくる案内をしっかり確認しましょう。
医療保険の、入院、手術、通院の給付金請求

では次は、入院や手術の時等の給付金請求について確認してみましょう。
こちらは各社見てみても比較的シンプルなので、おそらく生命保険金の請求と比べるとそこまで大変ではないかと思います。
給付金請求書(保険会社から送付)
事故状況報告書※事故の場合(保険会社から送付)
診断書(証明書)(保険会社から送付)
→病院の領収書や診療明細書で代替できる場合も
診断書(証明書)は保険会社指定の様式がありますので、前もってとっておこう!とすると提出できない書面を発行してしまうことにもなりかねません。
必要である、という認識だけもって置いて、先走って書面の作成を依頼することが無いように注意しましょう。
書類代が高くつきそうな時は?
ちなみに、診断書を病院で発行するときには費用が発生します。
病院によって費用は異なりますが、平均では3,500円程度。下は1,000円から、上は10,000円までと金額に幅があるそうです。
書面を用意してもらうのに自分でいくらか支払って、それで保険料の支払い対象にならなかったとなってはがっかりするどころか実際金額面でもマイナスが出てしまいます。
そこで保険会社によっては、請求したにも関わらず支払われないとなった時には診断書代金の相当額を負担すると定めていたり、請求する内容によっては診断書ではなく、発行するのにお金がかからない病院の領収書や診療明細書でも請求できるとしていたりという対応もあります。
ただ、明細書などでも代用できるとは言え、そもそも請求期限切れの保険金・給付金を請求したいという場合は明細書など手元に残っていることはほぼないはず。
請求窓口に『規定では期限切れとなっている請求を行いたい』と問い合わせを行う時に、診断書を作成してもらう代金の扱いはどうなるのか、というのも確認してみていただければと思います。
まとめ
以上、今回は『保険金・給付金請求に期限はあるのか?どのくらいなのか?』についてご紹介をしていきました。
最後に、内容を要約してポイントだけまとめておきます。
① 保険金・給付金請求に期限はある
② 期限は3年間
③ 期限が切れても請求できる可能性があるので、まずは問い合わせを行う
④ 請求漏れを起こさないように、下記の点に気を付ける
Ⅰ.病院の領収書を確認する癖をつける
Ⅱ.加入保険は家族と共通認識を持つ
Ⅲ.加入保険の内容はしっかり把握する
せっかく保険料を支払って保障の準備をしているのに、気づかなかった、知らなかったと請求漏れを起こすことが無いようにまずは気を付ける事が第一です。
そのうえで、知識として3年の請求期限がある、という事を知っておいていただければと思います。
また、加入保険の内容について把握できていないという場合は、プロのライフコンサルタントが加入中の保険を確認、説明したうえで、過不足がないかなども相談いただける無料相談サービスの利用がおススメです!
【保険無料相談.com】では、何度でも無料で保険についてのご相談をしていただくことが可能です。
準備している保障内容の説明はもちろん、公的制度や、お客様の状況も踏まえたうえでアドバイスをさせていただけますので、よろしければぜひこの機会にぜひご相談ください!