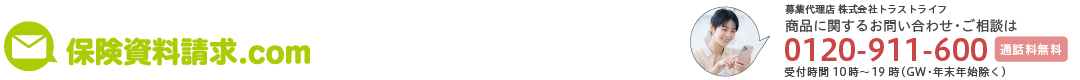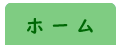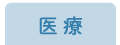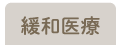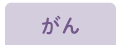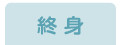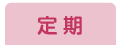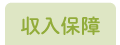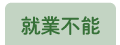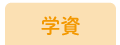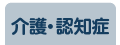初回投稿日:2021/3/20 最終更新:2023/3/24

今回お伝えするのは高額療養費を利用する際の注意点についてです。
今回の結論:制度適用外等の部分もあり、お金はかかる。保険や貯金での用意もしておくのがおススメ。
別の記事で高額療養費制度の基本をご紹介していますが、その記事では主に概要をお伝えしていて、注意点については簡単にしかご紹介していませんでした。
関連記事はコチラ⇒『【公的制度解説】入院しても医療費はかからない?確認必須の高額療養費制度について』
今回はそんな注意点について、改めて掘り下げてご紹介をしていきます。
特に、こんな方には是非確認いただきたい内容です!
・高額療養費制度があるから、医療費の心配はないと思っている方
・医療保険は不要!というようなコラムを見て保険の必要性に疑問を感じた方
・高額療養費制度の注意点は知っているが、実際どのくらいの費用が必要になるか知りたい方
「せっかく制度を利用したのにがっかり・・・」「思っていたの違う・・・」ということが無いように、ぜひこの機会に確認頂き、正しく理解していただければと思います。
また注意点は確実に知るために直接聞きたい、という方はコチラへ。
→自分に合った解決方法をプロに相談したいなら、無料で何度でも相談できる保険無料相談.com
手元に資料を用意してから検討したい、という方はコチラへどうぞ。
→資料で確認したいなら、医療保険を一括で資料請求、複数社比較検討できる保険資料請求.com
高額療養費制度の注意点3点
最初にお伝えしておくと、今回は高額療養費制度の基本は知っているという方向けに注意点をご紹介していくものです。
そのため、まずそもそもの高額療養費制度がわからない、よく知らないという方は、まず基本についてご紹介した記事からご確認下さい。
関連記事はコチラ⇒『【公的制度解説】入院しても医療費はかからない?確認必須の高額療養費制度について』
基本の内容は大丈夫という方は、ぜひこの続きをご覧ください!
今回の内容でお伝えしたい注意点は、下記の3点となります。
②最初の支払いは、原則として全額支払い
③対象外になる費用がある
それぞれの内容について確認していきましょう。
【注意点1】高額療養費制度はあくまで1ヶ月単位

高額療養費制度の基本についてご紹介した記事でも『一番注意いただきたいところ』とご紹介したのがこの内容です。
『【公的制度解説】入院しても医療費はかからない?確認必須の高額療養費制度について』の内容のおさらいになりますが、高額療養医制度は1ヶ月にかかる治療費について上限を設けるという制度です。
そのため、月をまたいで高額な医療費がかかった場合は、それぞれの月ごとに上限額までの自己負担が必要になります。
1回の入院に対する上限額を定めていたり、一連の治療に対する上限額を定めていたりするわけではありませんので注意が必要です。
平均の入院日数は?
これはあくまで参考値ですが、現在の平均の入院日数について確認してみましょう。
平均31日以上あれば確実に月をまたぎますし、短ければその心配は少なくなりますが、現状はどうなっているでしょうか。
厚生労働省の調査結果をご紹介します。
| 年齢 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 総数 | 32.3日 |
| 0~14歳 | 8.9日 |
| 15~34歳 | 12.2日 |
| 35歳~64歳 | 24.4日 |
| 65歳以上 | 40.3日 |
| 70歳以上 | 41.7日 |
| 75歳以上 | 45.0日 |
※出典元:厚生労働省『令和2年患者調査の概況』から抜粋し表を作成
この表から、年齢によって平均在院日数がだいぶ変わってくるのがわかりますね。
高齢の方の入院日数が長くなりがちなのは想像しやすいところではありますが、意外にも35歳~64歳の区分でも20日以上と長めの平均値になっています。
入院が月初か、月中か、月末かでも変わってきますが、20日以上にもなってくると入院が月をまたぐ可能性が高くなってきます。
そのため、35歳以上は『高額療養費制度は1ヶ月単位の上限額を定めているもの』という注意点をよく理解しておいていただきたい年齢であるといえます。
月をまたいだ場合の計算例
では、入院日数の統計を踏まえたうえで、入院が2ヶ月にまたいだ場合について計算してみましょう。
計算には高額療養費制度の基本の紹介記事で使った収約370~770万円だった場合の高額療養費制度の式を使い、医療費も同じく悪性新生物(がん)の推計の金額をつかって上限例をみてみます。
【高額療養費制度の自己負担算出の式】
月の上限額:80,100円+(医療費-267,000)×1%
【医療費の例】
悪性新生物(がん)の推計1入院当たり医療費 … 561,876円
※出典元:健康保険組合連合会『平成29年度 新生物の動向に関する調査』
1ヶ月の内に治療が収まった場合は高額療養費制度の基本の紹介記事でも確認した通り、計算はこのようになります。
80,100円+(561,876-267,000)×1%
=80,100円+2,948円
=83,048円
※小数点の金額は切捨て
1ヶ月の自己負担上限額:83,048円
では次に、治療が2ヶ月にまたがった場合を見てみます。
実際の1ヶ月目と2ヶ月目の上限額は、それぞれの月で医療費がいくらかかったのかによって変わりますが、今回は一番負担額が高くなる、ちょうど半分の金額ずつ医療費がかかった場合を想定して計算してみます。
1ヶ月の医療費 = 561,876円 ÷ 2 = 280,938円
80,100円+(280,938-267,000)×1%
=80,100円+139円
=80,239円
※小数点の金額は切捨て
1ヶ月の自己負担上限額:80,239円
2ヶ月合計での自己負担上限額:160,478円
1ヶ月にまとまって医療費がかかった場合は80,239円を支払えばよいのと比べると、ちょうど半々で月をまたいでしまった場合は負担額が約2倍近くになることがお分かりいただけると思います。
『上限額があるから大丈夫、8万円ちょっとでおさまるでしょ?』と思っていると、予想外の出費にがっかりする可能性があります。
計算例の金額を確認いただいたうえで、月をまたいで治療を受けた場合の支払いイメージももっておきましょう。
解決方法
この点の解決方法ですが、無理に月内に退院する、入院を遅らせて月初めに開始する、などといった『月をまたがないようにする!』といった方法は現実的とは言えません。
そのため、この注意点に対して取れる方法としては、シンプル・当たり前の事ですが『出費に対応できるようにすること』です。
方法としては下記の2つが考えられます。
②医療保険に加入しておく
たとえば、1ヶ月の上限額を、80,100円プラス上乗せ分で多めに9万円だと仮定します。
そうすると、自身で支払う金額としては2ヶ月で18万円、3ヶ月で27万円必要です。
このくらいであれば、貯金で用意しておくのも無理な金額ではないと思います。
また、医療保険での準備でも、単純に入院1日あたり5千円受け取れる内容で準備しておけば、9万円うけとるのに18日間、18万円受け取るのに36日間、27万円受け取るのに54日間の入院となりますので、入院日数からしても『足りなくなる』という事はなさそうです。
ただし、医療保険の場合は、1回の入院では30日まで保障する、60日まで保障すると条件が違う場合がありますし、また入院開始時点でまとまった金額が受け取れるものなどもあり種類は様々ありますので、医療保険で準備を考える時には色々比較してみてみましょう。
→自分に合った保険をプロに相談したいなら、無料で何度でも相談できる保険無料相談.com
→さまざまな医療保険をご紹介!一括で資料請求、複数社比較検討できる資料請求サイトはこちらから
【注意点2】最初の支払いは、原則として全額支払い

次の注意点は、実際の支払いのときに慌てないように知っておいていただきたい内容です。
高額療養費制度の基本は『1ヶ月間の医療費の上限額を定め、それを超えた場合に超過分を支給する』というもの。
そのため、原則として窓口での支払い時は、高額療養費制度適用前の、医療費の自己負担分全額を支払う必要があります。
最初から上限額の支払いのみと勘違いしていると、足りない分を慌てて準備しなければならなくなりますし、また、差額は後から支給されるとはいえ、払い戻しまでのお財布事情は苦しくなってしまうかもしれません。
慌てずに済むためにもしっかり認識しておきたいところです。
窓口負担額の計算例
実際どのくらいの金額の差が発生するのか、簡単に確認しておきましょう。
何度か例で取り上げている『悪性新生物(がん)の推計1入院当たり医療費…561,876円』の金額で計算してみると、健康保険適用で3割負担の方の場合、一時的な窓口負担額は約168,562円です。
仮にこの入院が1ヶ月以内に収まっていたとすると、高額療養費を適用した上限額は83,048円となるので後から差額分の85,514円が払い戻されるようにはなります。
そう考えると、支払い時には最終的な自己負担額の倍の費用が必要です。
この推計の数値の場合はこのくらいの違いで収まっていますが、高額になりがちな疾病を確認してみると、別のデータで、循環器系の疾患では1回の入院当たり『939,671円』かかるというデータもあります。
“出典元:厚生労働省『令和2年度 医療給付実態調査』、疾病分類・制度別・1件当たり診療費の表より協会(一般)部分を抜粋”
この場合になると、健康保険適用で3割負担の方の場合で自己負担額は約281,901円、1ヶ月以内に収まった場合の高額療養費の上限は約86,308円なので、最終的な負担額の3倍近くの金額を一時的に負担しなければなりません。
疾病や医療方法などによって最初の負担感はだいぶ変わってきますので、注意が必要です。
超過分支給までのスケジュール
一時的に負担した場合に気になるのは、上限額を超えた分の払い戻しはいつ受けられるのか、という点。
厚生労働省の資料によると、支給までにかかる時間は受診した月から少なくとも3ヵ月程度という記載があります。
高額療養費制度の基本の流れとしてはこのようになるので確認しておきましょう。
①病院の窓口で、健康保険が適用された治療費について全額を支払う
②自身が加入している健康保険組合などに申請書を提出する
③支払ってから少なくとも3ヵ月以降に、健康保険組合や協会けんぽ等から超過分が払い戻される
より具体的な手続き方法や支払時期などは、加入している健康保険組合や協会けんぽなどによって異なる可能性があるので一度確認していただければと思います。
ただなんにせよ、支払った翌日にすぐに払い戻される訳ではない事は覚えておきましょう。
解決方法
この窓口負担額の問題に関しては、1つ明確な解決方法があります。それが『限度額適用認定証』です。
ただし、状況によってはこの方法が取れない場合もありますので、他の候補も含めると解決方法は下記の4つが考えられます。
②高額医療費貸付制度を利用する
③貯金をしておく
④医療保険に加入しておく
貯金と医療保険に関しては『使えるお金を用意しておく』という意味では先ほどと同じ。
医療保険に関しては、先ほどご紹介した通り下記のサイトで見ていただければ選択肢はある程度ご理解いただけると思います。
→さまざまな医療保険をご紹介!一括で資料請求、複数社比較検討できる資料請求サイトはこちらから
※因みに、医療保険の場合は不備のない必要書類を提出し、問題なく確認が取れれば約5営業日以内に支払われるので、高額療養費制度の払い戻しを待つよりはスピード感は早いと思います。
そのため、ここではあまり聞きなじみがないであろう『限度額適用認定証』と『高額医療費貸付制度』について補足していきます。
解決方法補足、限度額適用認定証について
まだ入院をしていない、もしくは入院を始めたばかりならこの書面を準備するのが一番おススメです。
この書類は、健康保険証を合わせて提出すれば、なんと最初から上限額のみの支払いでよくなるとても便利な書類です!
『最初の支払いは、原則として全額支払い』とご説明していましたが、なぜ“原則”とついていたかというと、この書類を用意しておくことでそのネックを解消することができるため。
ただし当然ながら、この書面は支払いを行う前までに病院に提出できないと意味がありませんので、その点だけは注意してください。
▶限度額適用認定証の取得方法
この書類は、自身が加入している健康保険組合や協会けんぽなどに必要書類を提出することで取得することができます。
ただし提出してから発行されるまで1週間程度かかるところが多いようなので、退院が近くなってからだと間に合いません。
医療費がたくさんかかってしまう予定が立った場合はすぐに、もしくは入院を開始したらすぐに手続きを始めるようにしましょう。
解決方法補足、高額医療費貸付医制度について
次に『高額医療費貸付制度』について内容のご紹介をしていきます。
この制度は、限度額適用認定証が提出できず、一時的に自己負担分の医療費を支払う必要がでた場合の救済策。
内容としては、医療費の支払いが難しい時に、無利息でお金を借ることができる制度です。
治療費の支払いに充てるための資金を高額療養費が支給されるまでの間借りることができ、高額療養費制度で払い戻される予定の8割程度の額の借入が可能です。
たこの制度を利用できるかどうかやその詳細はご加入の健康保険組合や協会けんぽなどによって異なる場合があり、詳細についてはご自身で問い合わせていただく必要がありますが、こういった制度があることは覚えておきましょう!
【注意点3】対象外になる費用がある
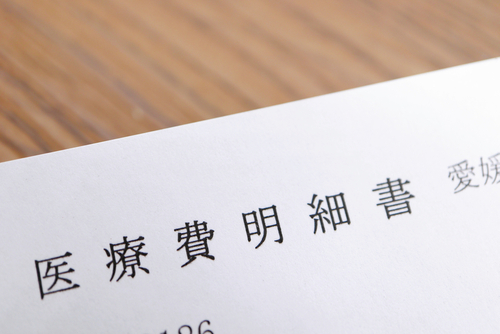
では注意点3つめの内容、対象外の費用についてのご紹介に入ります。
高額療養費制度は『医療費の1ヶ月上限額を定める制度』のため、治療を受ける中でかかってくる費用でも医療費ではない部分に関しては適用されず、その分は上限額を超えて支払いが必要になります。
例えば、入院中に購入したテレビカード代や売店での購入費などが対象外になるというのは理解しやすいところではないでしょうか。
この他に、費用が大きくなりがちで、かつ高額療養費制度の対象外になるのはこのようなものがあります。
②食事代
③先進医療の技術料
それぞれの費用について見ていきましょう。
差額ベッド代
簡単に言うと、こちらは大部屋以外を希望した時にかかる部屋代です。
感染症のため本人の希望は関係なく大部屋に入れられないときなど、治療上の必要があり個室に入院した場合は個人負担にはなりませんが、そうでない場合は入室した部屋のタイプによって1日ごとに費用が発生します。
4人部屋よりは2人部屋、2人部屋よりは1人部屋といったように、少人数になればなる程、差額ベッド代が高くなるのが一般的です。
具体的にどのくらいの金額になるか、厚生労働省の調査結果からご紹介します。
| 1日当たり平均徴収額(推計) | |
|---|---|
| 1人室 | 8,221円 |
| 2人室 | 3,122円 |
| 3人室 | 2,851円 |
| 4人室 | 2,641円 |
| 合計 | 6,527円 |
※出典元:厚生労働省『主な選定療養にかかる報告状況』令和2年7月1日現在の個所を抜粋
1人部屋は値段がとびぬけて高くなっていますが、基本ベッドの上で過ごす入院生活ですから、他の人が気になる、静かに過ごしたいと考えて1人部屋を選択する場合も多いと思います。
こちらは入院費用が大きく変わってくる可能性があるところですので、しっかり確認しておきましょう。
食事代
次は食事代についてです。
病院食の値段は平成30年4月から1食460円に値上がりし、今は1日3食で1,380円かかります。
これだけ見た時の負担感はそこまで大きい印象はないですが、積み重なれば確実に負担は増えてきます。
また、食事代は希望する・しないではなく、原則はかかってくる費用ですので、この部分は覚えておきましょう。
先進医療の技術料
最後は先進医療の技術料です。
まず、先進医療とは何かというと『健康保険適用になる前の先進的な医療技術のため、10割自己負担で受ける治療』であり、なおかつ『厚生労働省が先進医療と認定している治療』の事を言います。
(詳しくはまた別でご紹介をする予定です!)
健康保険適用になる前ということは、同時に高額療養費制度の対処にならないという事でもあります。
自己負担3割ではなく10割負担、高額療養費制度の対象にもならないとなると、当然治療にかかる技術料はすべて自分で払わなければいけませんので、その費用負担は重くなりがちです。
実際どのくらいかかるものなのかを確認いただくために、先進医療のなかでも、年間実施件数の多い治療の技術料を2つ例としてご紹介してみます。
| 先進医療技術名 | 平均入院日数 | 年間の年間の実施数 | 平均費用 |
|---|---|---|---|
| 陽子線治療 | 14.9日 | 1,293件 | 3,207,847円 |
| 重粒子線治療 | 5.3日 | 562件 | 3,361,088円 |
出典元:厚生労働省『令和4年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について』
見ていただいてお分かりの通り、これらの治療を受ける場合300万円前後の費用が必要です。
先進医療のすべてで同等の費用が必要になるわけではないですが、リスクに備えるという観点では一度対応策について検討は必要だと思います。
対象外の費用は意外とある
以上、具体例として3つの費用をご紹介しました。
最初に些細な例としてご紹介したテレビカード代や売店での雑貨類の購入などこまごまとした出費もありますが、正直そのあたりの多少の出費であれば貯金からの支払いで問題ないと思います。
ですが、入院日数分は確実にかかってくる食事代や、個室を希望した場合の差額ベッド代、多額の費用が必要になる先進医療の技術料などを考えると、高額療養費制度があるから治療費の心配は不要とは言いづらくなります。
せめて先進医療の費用分だけでも、対応の手立ては考えておきましょう。
解決方法
高額療養費制度対象外の費用、特に先進医療の費用負担に関しての準備方法ですが、これも2つ対応策が考えられます。
②医療保険に加入しておく
ただ、できればこの点については医療保険での準備がおススメです。
その理由としては、『使えるお金を用意しておく』という意味では貯金でももちろん対応できますが、先進医療の治療は金額が大きいものも多く、治療を受けるとなった時に十分な額が準備できているかなどの問題もあるためです。
医療保険で準備するポイントは、ただ加入するのではなく、『先進医療特約』もしくは『先進医療特則』という保障を付けた内容で準備する事です。
細かい保障内容は商品によって異なることもありますが、基本の保障内容としては先進医療の技術料を実費保障してくれるというもの。
上限額は2,000万円までとしているところが多いので、300万円近い技術料が必要になる『陽子線治療』『重粒子線治療』を受けたときにも対応できます。
これから医療保険の加入を考えている方は、この特約には注目して保険を選んでみましょう。
→新たに保険に加入するのに便利、比較に便利な一括資料請求ができるサイトはこちらから
また、現在医療保険をご準備の方でも保障内容に先進医療保障が入っていない可能性もありますので、内容についてうろ覚えなら一度確認するのがおススメです。

→自分の加入保険に不安がある方向け、無料の保険相談の予約はこちらから
医療保険で準備をしておけば先進医療の技術料の準備だけでなく、そのほかの食事代・差額ベッド代に関しての費用も入院一時金の保障や入院日額の保障で対応することができますので、まとめて準備してしまいましょう!
まとめ
今回は、高額療養費制度の注意点について、3つをピックアップしてご紹介しました。
とてもありがたい制度ではありますが、それだけでは対応しきれない部分があるということもお分かりいただけたでしょうか。
最後に改めて簡単に注意点と解決方法についてまとめておきますので、しっかりおさらいしておきましょう!
注意点と解決方法一覧
月をまたいで多額の医療費がかかった場合、8万円ちょっとの上限額がそれぞれの月で必要になる。
治療の始まりから終わりまでかけて、8万円ちょっとの上限額で済むわけではない。
【解決方法】
『貯金で準備しておく』
『医療保険に加入する』
何もしなくても上限額のみの支払いを行えばいいと思っていると、病院窓口での精算時に慌ててしまうことも。
原則として、窓口では一度、健康保険を適用した3割分の自己負担額は一度支払わなければならない。
【解決方法】
『限度額適用認定証を発行する』
『高額医療費貸付制度を利用する』
『貯金をしておく』
『医療保険に加入しておく』
おすすめは『限度額適用認定証を発行する』だが、退院前に間に合わない場合は使えないため注意。
医療費に当たらないところは高額療養費制度で定められている上限額の内に入らない。
金額が大きくなりがちだが含まれない例としては、差額ベッド代、食事代、先進医療の技術料などがある。
【解決方法】
『貯金をしておく』
『医療保険に加入しておく』
おすすめは医療保険。特に先進医療の技術料負担に関しては医療保険の特約で準備しておいた方が安心できる。
自身にあった解決方法の選択を
以上、簡単なおさらいでした!
ご確認頂いた通り、注意点1つに対して解決方法はそれぞれ2つ以上あげてみました。
貯金が充分にある方であれば、先進医療特約を付けた最低限の医療保険のみの準備で安心いただけるという方法もありますし、貯金が充分と言えないという方であれば、貯まるまでの間は入院費をまかなえるだけの保障を、保険料が抑えられた掛け捨てタイプの医療保険で準備をしておくという方法もあります。
ぜひ理由もなく印象だけで『貯金でいいかな』と判断したり、『保険に入らなきゃ!』と慌てたりせずに、総合的に見てご自身に合った解決方法を選んでいただければと思います。
また、途中でもご紹介はしていましたが、それでもよくわからない、十分に備えられているか不安・・・と言う場合は、最初からプロのライフコンサルタントに相談いただける無料相談サービスの利用をおススメしています!
【保険無料相談.com】では、何度でも無料で保険についてのご相談をしていただくことが可能です。公的制度はもちろん、お客様の状況も踏まえたうえでアドバイスをさせていただけますので、よろしければぜひこの機会にぜひご相談ください!