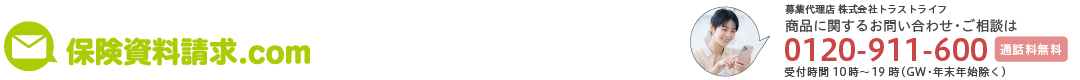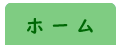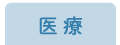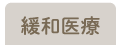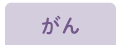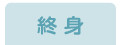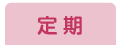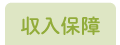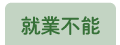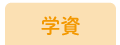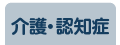収入保障保険の概要等をまとめの記事でご紹介してみましたが、前回のまとめの記事ではそもそもの必要性の部分についてはあまりお伝えしていなかったかと思います。
そこで今回は基本に立ち戻って、収入保障保険の必要性について改めて説明していきたいと思います。
💡#収入保障保険 ってどのくらい必要?
一般的な生命保険より割安!とよくおススメされる収入保障保険。
でも、今の自分の給料まるまる準備しようとすると保険料にびっくりするかも!
実は収入イコールで準備する必要はないので、まずは考え方を知ることが必要です!
— 保険資料請求.com (@hoken_siryo) June 9, 2020
ぜひ収入保障保険を検討中の方も、そもそも備えるべきかわからないという方もご確認してみてください。
結論から
まず、収入保障保険は必要かというと、これは『ケースバイケース』というのが本当です。
実際のところ収入保障保険に限らず、保険全般「自分では対応しきれない部分を補てんするためのもの」なので、保険をかけなくてもしっかり用意さえできていれば本当は不要といえます。
なので、収入保障保険の必要性についてより正確に言うのであれば
万が一の時、遺族の生活を支えられるだけ準備ができている人なら不要
ですし、
万が一の時、遺族の生活を支えられるだけの準備ができていない人なら必要
ということになります。
一番難しいのが、この遺族の生活を支えられるだけの金額を把握することです。
その家庭によって家族構成も違えば、生活スタイルも違う、考えているライフプランも違う・・・となると、必要な額も大幅に変わってきて一概には言えません。
しかも、必要な額が分かったからと言って、それを実際に用意できるかどうかというのはまた別問題です。
具体的に計算してみる。
まずはモデルケースを使って、実際どのくらいの資産があれば、遺族の生活を支えることができるのかを具体的に探ってみましょう。
まとめ記事で書いた遺族年金の話にも触れていきます。
★まとめ記事【収入保障保険マニュアル!完全保存版】はこちら
ただ途中で計算が面倒くさい、難しいと思ったら、結果必要な額まで飛んでください。
その時はコチラ⇒『【Step4】出費と収入を計算する』
それも飛ばして、私の場合は実際必要なのか、必要ならいくら金額はいくらなのか知りたい!という方はプロに相談しましょう。
その時はコチラ⇒『保険無料相談.com』
【Step1】算出する家庭の基本情報を確認する
今回は、下記の家庭構成をモデルケースにします。
※あくまでここからは概算になります。目安として確認してください。
家族構成
| 年齢 | 職業 | 平均標準 報酬月額 |
|
| 夫 | 30歳 | 会社員 | 40万円 |
| 妻 | 30歳 | 専業主婦 | – |
| 長男 | 3歳 | – | – |
| 長女 | 1歳 | – | – |
■月の生活費
30万円
■住まい
賃貸
【Step2】遺族の生活にかかる費用を計算する
まず、現在30歳の女性の平均余命は57.51年の為、88歳までの生活費が必要と仮定します。
平均余命出典元:H27年:厚生労働省『簡易生命表』
長男が独立するまで19年、長女が独立するまで21年あるので、
必要な生活費の推移はこのくらい、と目安を立てます。
生活費計算
| 年数 | 家族の年齢 | 月の生活費 | 変化 |
| 19年間 | 妻49歳 長男22歳 長女20歳まで | 30万円 | 長男は翌年から独立(生活費5万減) |
| 2年間 | 妻51歳 長女22歳まで | 25万円 | 長女は翌年から独立(生活費5万減) |
| 37年間 | 妻88歳まで | 20万円 |
それぞれでかかる費用を計算すると下記のとおりです。
19年間×12ヶ月×30万円=6,840万円
2年間×12ヶ月×25万円=600万円
37年間×12ヶ月×20万円=8,880万円
合計:1億6,320万円
妻が一人になってからの生活費が高いと感じるかもしれませんが、夫がもしも30歳で亡くなったらと仮定しているため、住まいは持ち家でなく賃貸という設定で家賃分を少し高めに設定しています。
【Step3】公的制度で給付される額、妻の収入を考える
次に、貯金で準備しておかなくとも確保できる金額を考えてみましょう。
まず妻が88歳までの生活費が必要という仮定は同一で、公的な制度で受け取れる額を計算します。
遺族年金・老齢年金
| 年数 | 家族の年齢 | 年金の種類 | 支給年額 |
| 15年間 | 妻45歳 長男18歳 長女16歳まで | 遺族厚生年金+遺族基礎年金 | 641,300円+1,229,100円 |
| 2年間 | 妻47歳 長男20歳 長女18歳まで | 遺族厚生年金+遺族基礎年金 | 641,300円+1,004,600円 |
| 18年間 | 妻65歳まで | 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算 | 641,300円+585,100円 |
| 23年間 | 妻88歳まで | 遺族厚生年金+老齢基礎年金 | 641,300円+780,100円(満額と仮定) |
それぞれで支給される額を計算すると下記となります。
15年間×187,04万円=2,805.6万円
2年間×164,59万円=329,18万円
18年間×122,64万円=2,207.52万
23年間×142,14万円=3,269,22万
合計:8,612万円(万以下の単位は四捨五入)
他公的制度から
遺族年金だけだと、パッと見た限りでもあからさまに必要な金額に対して足りないので、もう少しどうにかできないのか考えてみます。
そこで計算に入れたいのが、子供がいることによってもらえる公的制度からの給付。
実際には他にも手当はありますが、妻の収入によってもらえる額が前後してしまうので今回は児童手当と児童育成手当をピックアップして考えてみます。
| 年数 | いつまでもらえるか | 種類 | 支給年額 |
| 2年間 | 長女3歳まで | 児童手当 | 12万円 |
| 12年間 | 長男15歳まで別途長女15歳まで | 児童手当 | 6万円×2人 |
| 15年間 | 長男18歳まで | 児童育成手当 | 16.2万円 |
| 17年間 | 長女18歳まで | 児童育成手当 | 16.2万円 |
実際の受取合計額を合計すると下記となります。
2年間×12万円=24万円
12年間×12万円=144万
15年間×16.2万円=243万円
17年間×16.2万円=275.4万円
合計:686万円(万以下の単位は四捨五入)
パート勤め
公的制度だけではまだまだ足りないことが明確なので、働きに出ることも考えてみます。
時給:業種によってばらつきもありますが、ここは現実的に時給1000円の仕事をするとします。
勤務時間:お子さんが小さいうちであればシフトは短時間になりますし、また夏休み・冬休み、GW等休みの期間はお子さんが家にいるので仕事で外に出るのは難しいでしょう。逆にお子さんが大きくなれば安定してシフトに入れます。
プラスマイナスを考えて、ここは全期間1日5h、月18日シフトに入るとして、月90h働くとします。
期間:下の子が小学校に入る35歳から初めて、60歳まで、25年間働きます。
さて、では自分で稼ぐことができる見込み分のお給料を計算しましょう。
1000円×90h×12ヶ月×25年間=合計:2,700万円
合計
最後に得られる見込みの収入を全て足してみます。
遺族・老齢年金:8,612万円
その他公的制度:686万円
勤労収入:2,700万円
合計:1憶1,998万円
【Step4】出費と収入を計算する
ではいよいよ、モデルケースの場合だといくら貯金があれば遺族の生活費をまかなえるのかを結果します。
ここまでで計算した出費と収入とを計算してみましょう。
出費:1億6,320万円
収入:1憶1,998万円
不足:-4,322万円
必要貯金額決定、4,322万円
計算の結果、モデルケースの場合だと30歳時点で約4,322万円の貯金があれば計算上は足りる結果になりました。
無ければ、収入保障保険は検討の価値あり、といえるかと思います。
今回は妻が88歳までの必要費の確保を目的として計算し、公的制度もプラスした概算です。
もちろん、今回はあくまで概算ですし、家庭によって生活費も違いますので全員これだけかかる!とは言い切れません。
逆に公的年金は仕事や加入期間で額が変わるので、全員がこれだけ貰える!ということも言い切れません。
ただプラスマイナスを考えても、今回の計算で出した不足する金額の4,322万円が0円になるということはあまり考えづらいかと思います。
まずはこの結果については、概算ではありますが、収入保障保険の必要性を考える時に一つの情報として見ていただければ嬉しいです。
また備えるべき金額を何となくで考えるよりは具体的にこう考えればいいんだな、と思っていただければと思います。
ただそうは言ってもこれを自分の状況で、自分自身で計算するのは実際大変です。
いくら必要かはまだ計算できたとしても、補てんできる額の計算の方が問題。公的制度も知っておかないと把握ができません。
まずは情報を得るという意味で、無料の相談サービスをご利用されるというのも一つの手だと思います。
お悩みになって時間を使ってしまうよりは、一度話を聞いてみて考えを整理するのがおススメです。