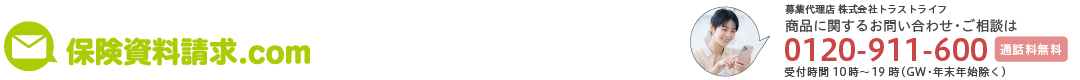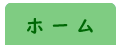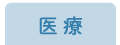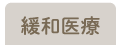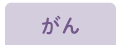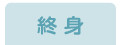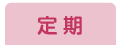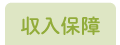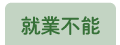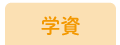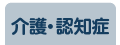結婚は人生の一大イベント!
このタイミングで、そろそろ何か保険に入ろうかと検討を始める方や、加入している保険について確認をしようと考える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
家族が増え環境が変われば、必要になってくる保障も変わってきます。
そこで今回は、新たな保険の加入や見直しを考える際のポイントと注意点をわかりやすく解説をしていきます。
ぜひ、今まさに検討を始めている方、これから結婚・出産を控えている方は確認してみて下さい!
最初に夫婦ですべきこと

何事も始めが肝心!
「最初に話しておけばよかった・・・今更言い出しにくい・・・」なんて後から後悔しなくていいように、最初にすり合わせていたほうが良い事というのは様々あります。
日々の生活を円満に送るためという意味だと『家事分担のルール』や『ケンカ・仲直りのルール』などがよく話題に上がりますよね。確かにそれは大事!
ただそれと同じくらい、もしくはそれ以上に大事にして欲しいのは、これからの人生設計にかかわるような部分についてのすり合わせです。
人生設計のすり合わせ
人によって思い描く人生は様々。
将来的にはこうしたい、ああしたい・・・という考えによって、話題に上がる内容は多岐にわたると思います。
一般的な例でいうと、このあたりはぜひ話しをしていただきたいところです。
●仕事、働き方はどうするか?
●子どもは欲しいか?教育方針は?
●賃貸か持ち家か?
●お金に関して現在状況はどうなっているか?
1つずつ簡単にご説明していきます!
仕事はどうするか?
今は共働きの世帯が多数派の印象がありますが、厚生労働省のデータによると、共働き・専業主婦の世帯数はこんな感じでした。
| 1980年 | 2000年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 共働き | 614万世帯 | 942万世帯 | 1,129万世帯 |
| 専業主婦 | 1,114万世帯 | 916万世帯 | 664万世帯 |
出典:厚生労働省 平成29年版 厚生労働白書
データは2016年時点なので、もしかしたら現在はまた数値は変わっているかもしれませんが、昔と比べ共働き世帯が増加している、というのは確かですね。
それでも約37%の世帯は専業主婦家庭。
結婚を機に仕事を辞めたい・やめて欲しいという要望があるのであれば、しっかり世帯収入を把握するようにお給料面のお話をしましょう。
それとは逆に、結婚後も仕事を続けると決めた場合は、こんなところも考えていかなければいけません。
・フルタイムで続けるのか時短勤務にするのか?
・正社員なのかパートなのか?
・同じ職場か、別の職場を探すか?
子どもの有無や現在の環境、自分の希望、配偶者の考えも加味して考えていきましょう。
子どもは?
子どもを希望するかどうかは、人生のマネープランニングに大きな影響が出てくるので大事なポイント。
希望する場合は、下記の項目について決めておくと計画が立てやすいです。
・何歳までには産みたい
・何人ほしい
・進路は公立、私立どちらを予定するか
他にも海外留学や医大・音楽大など、教育方針に何かこだわりの点があるという場合は、その分の資金計画も必要ですね。
さすがに全部今決めるのも難しいですし、その通りいく保証もないですけど、ある程度目安をたてて準備をしてくことは大事です!
住まいは?
また、人生の三大費用に上げられる住宅費も、人生設計やマネープランニングの上では欠かせないポイントになります。
例えば考えられる選択肢としてはこんな感じ。
・生涯通して賃貸の予定
・住宅を購入希望で何歳頃を予定する
・どちらかの実家で同居する
・実家に住むけどリフォーム前提
住宅購入を希望する場合は、特に資金計画が必須です!
希望はしっかり夫婦間で出し合って、共通の意識を持てるようにしましょう。
お金の現在状況は?
お金関連で一番大事なのはここです!
ここまでで出てきた仕事・子ども・住まいなどの『将来に必要になるお金』のことも大事ですが、現在のお金の状況についても明確にしなければ計画は立てられません。
まずはお互いのお金の事情について、しっかり共有して正しい認識を持っておきましょう。
例えばこんなことです。
・貯金はいくらある?
・奨学金返済はある?いつまで、いくらある?
・車や借入など、現在ローンがある?いつまで、いくらある?
・保険等の個人の固定費はいくら?
計画的に貯金の目標を立てていくときには、まず現在の『出ていくお金』に注目しましょう。
また共働きだと、お互いの財布は別で、相手の収支については全く知らない・・・という家庭も多いようですが、せめて最低限お互い可能な貯蓄額を明確にしておく、ということはしておきましょう。
結婚での保険加入・見直しでのポイント

前提が長くなってしまいましたが、いよいよ本題に入ります!
前の項目の「1.5お金の現在状況は?」でも固定費である保険料について触れていますが、ここは毎月かかるコストなので「家計の出費」としては見逃せない所です。
ただし、「節約のため!」と言って全く用意しないと万が一の時に不安が残りますし、かと言って過剰な保障になっても、毎月の負担額が増えるのでお勧めできません。
そのため、新規加入・見直しを適切に行うための判断材料を揃えるところから初めていきましょう!
考える順番としてはコチラです。
①リスクを考える
②お金を見える化する
③優先順位を明確にする
④(既加入保険があるなら)現在の加入保険の内容を吟味する
1つずつ説明していきます!
リスクを考える
最初に「そうなってしまっては困る・・・」「ここが不安・・・」ということをリストアップします。
これは各家庭で様々あると思いますが、代表的なのは大きく分けてこの4つではないでしょうか。
●配偶者の死亡
→葬祭費用
→遺族の生活費
●自身、配偶者の病気、けが
→医療費の出費
→収入減少
●教育費の不足
●老後資金の不足
お金を見える化する
先ほどあげた4つのリスク・不安ですが、それぞれについて、闇雲に心配をしても不安になるだけで正しい準備はできません!
また、家族から・知り合いから勧められた保険を準備しても、本当にその内容・保障額が自分にも適切とは限らないので、ここはしっかり『不安を数字化して、見えるようにする』という作業が必要です。
ここでは例をあげて、参考として見ていただける数字、計算をご紹介していきます。

●配偶者の死亡
→葬祭費用
どのくらいの規模で行うか、どこに頼むのかにもよりますし、地域性もあるものなので一概には言えませんが、目安の金額としてはこちらです。
【葬儀費用:目安】
| 火葬のみ | 約20万円 |
|---|---|
| 家族葬 | 約60万円 |
| 一般葬 | 約100万円~ |
一般葬というのは、いわゆる通夜・告別式・火葬の一通りを行うお葬式の事を指します。
もちろん、参列者が多かったり、こだわりを持った送り出し方を希望したりすると費用はどんどん高額になります。
そのため一概にいくらあれば十分!とは言えないですが、とりあえず100万円あれば、お葬式をあげること自体は可能のようです。
お墓を新しく作る場合を考えるならさらに費用がかかるので、合計で200万円~となります。
→遺族の生活費
家計の収入を担っていた方が亡くなってしまった場合には、残された家族の生活を維持していくためのお金が必要になってきます。
遺族の生活費を維持するための金額を計算するにはざっとこのあたりの数字が必要です。
・のこされた配偶者が何歳まで生きる見込みか
・現在の月の生活費はいくらか
・子供がいる、もしくは欲しい場合は予測の教育費はいくらか
・公的制度でどのくらい補填できるか
・貯金はいくらあるか
計算方法の例としてはこんな感じ。
② 現在の生活費×0.8で月の生活費を計算(亡くなった方の分2割減ると仮定)・・・A
③ A×12ヶ月=1年の生活費・・・B
④ B×配偶者の平均余命=残された配偶者の今後の生活費・・・C
⑤ 子どもが欲しい場合は予定の教育費と生活費が2割増えると仮定して『B×0.2』
C+教育費+B×0.2×22年間・・・C´
⑥ 公的制度の『遺族年金』『老齢年金』を計算し、
さらに子どもがいる・欲しいなら『児童手当』『児童育成手当』を計算・・・D
⑦ 不足分を計算。『CもしくはC´-D-貯金-その他収入=不足分』
計算の内容を詳しくご説明すると、非常に長くなってしまうので・・・。
ここは以前にまとめた記事があるので、ご興味があればぜひ下記からご確認下さい。
→『収入保障保険の必要性について』

●自身・配偶者の病気、けが
→医療費の出費
もしも病気やケガで入院が必要になった場合を考えると、医療費が一体どのくらい負担になるかも心配ですよね。
でも基本的に医療費は3割負担だし、高額療養費制度もあるし、そんなに大金が必要になるのかな?と疑問の方もいるはず。
そこで参考として、下記のデータをご紹介します。
・入院時の自己負担費用
・1日当たりの自己負担額
| 自己負担額 | 割合 |
|---|---|
| 5万円未満 | 7.6% |
| 5~10万円未満 | 25.7% |
| 10~20万円未満 | 30.6% |
| 20~30万円未満 | 13.3% |
| 30~50万円未満 | 11.7% |
| 50~100万円未満 | 8.4% |
| 100万円以上 | 2.7% |
| 一日当たり自己負担額 | 割合 |
|---|---|
| 5千円未満 | 10.6% |
| 5千~7千円未満 | 7.6% |
| 7千~1万円未満 | 11.1% |
| 1万~1.5万円未満 | 24.2% |
| 1.5万~2万円未満 | 9.0% |
| 2万~3万円未満 | 12.8% |
| 3万~4万円未満 | 8.7% |
| 4万円以上 | 16.0% |
*治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品などを含む。高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額
「令和元年度 生活保障に関する調査(速報版)」
一部の高額帯によって平均が引き上げられている感じもありますので、一番分布が多い所に注目して見ましょう。
自己負担額は30.6%が該当する10~20万円未満を1つの目安に。
1日あたりの自己負担額は、24.2%が該当する1万~1.5万円を1つの目安にしていただければよいのではと思います。
→収入減少
出ていくお金の治療費についてご紹介しましたが、次は、入ってこなくなるお金についてです。
入院中や退院をして療養が必要な場合は、仕事を休まざるを得ないことが考えられます。
ただし仕事を休んだからと言って、会社勤めの方であればいきなりその間のお給料が0になることはありません。会社勤めの方であれば健康保険の「傷病手当」があるからです。
傷病手当がある場合、休業4日目から最長1年6ヶ月は、それまでの給与の2/3程度の手当を受け取ることができます。ただ、逆に言えば1/3の収入源にはなりますので、そこは注意しておく必要があります。
また傷病手当があるのは会社勤めの健康保険に加入している方なので、国民健康保険に加入している自営業の方は傷病手当を受け取れません。
自営業の方は特に、ここはしっかり対策を考えておきましょう。

●教育費の不足
次に教育費についてです。
1人当たり大体1,000万円かかるなんて言われますが、実際のところ進路次第です。
詳しくはこちらの記事で過去にまとめているので、興味があればぜひご確認ください。
→『1人当たり教育費は最低1,000万円』は本当か?!仕送り額の平均も含めて大検証!
ここではざっくりと、一番お金がかからない進学先を選んでいけば1,000万円程度。
公立で進み、大学だけ私立文系に行ったとすれば、1,100万円程度になる、という紹介にとどめておきます。
覚えておきたいのは、トータルで1,000万円かかるとはいえ、全額1度に支払う訳ではないという事。
大きく負担が出てくるのは各入学のタイミング、特に大学入学時です。
公的制度で児童手当というのもあり、きちんと貯めておけば200万円近くは準備できます。
足りない金額を使うタイミングまでに、しっかり準備できるように方法を検討しておきましょう。

●老後資金の不足
最後に老後資金の不足についてです。
少し前に、「老後資金は2000万円不足する」という話題が出た事もあり、年金に対する関心は高まったように感じます。
本当に2000万円不足するのかというと、受け取れる額に個人差がある国民年金と厚生年金の収入と、さらに個人差が大きい生活環境や生活水準等の出費、希望する老後の過ごし方で変わってくるので一概には言えません。
目安として、統計をもとに計算できる内容を見てみましょう。
流れとしては下記です。
①今の年齢から平均で生きる年数(平均余命)を知る
②高齢者世帯(無職)の1ヶ月の家計収支からマイナスを知る
③平均余命の無職年数×家計収支マイナス=老後不足分
順を追ってみていきます。
①平均余命
今の年齢から平均で何年生きるかのデータです。
現状だと、例えば30歳男女だとこのようになっています。
| 性別 | 平均余命 |
|---|---|
| 男性 | 51.88年 |
| 女性 | 57.77年 |
出典:厚生労働省「平成30年簡易生命表の概況」
つまり、現在30歳の男性であれば81.88歳まで。
現在30歳の女性であれば87.77歳まで平均で生きる、と言えます。
②高齢者世帯の家計収支
次は1ヶ月の生活の不足分を見てみましょう。
総務省発表の、『家計調査報告-家計収支編(2019年)』のデータから数字を抜粋してみます
▶夫65歳以上、妻60歳以上で構成する無職の世帯
家計収支:-33,269円
▶65歳以上の無職単身者世帯
家計収支:-24,033円
③老後不足分
①を参考に、30歳の場合で65歳から何年老後があるか計算しましょう。
男性であれば65歳以降の余生は16.88年。
女性であれば65歳以降の余生は夫婦がそろうのが16.88年、一人になって5.89年です。
つまり、不足分をごく簡単に計算するとこのようになります。
年間の不足額(夫婦):33,269円×12ヶ月=399,228円
年間の不足額(単身):24,033円×12ヶ月=288,396円
夫婦そろって過ごす老後の不足額:399,228円×16.88年=6,738,968円
妻一人で過ごす老後の不足額:288,396円×5.89年=1,698,652円
合計:8,437,620円
と、いうことで、統計から生活費のみを考えると、約844万円不足するという計算になりました。
ただ、変わらずずっとこの生活をするのか?高齢で1人になった時もそのまま生活するのか?というちょっと現実的ではない部分もあります。
本当なら『施設に入居』『バリアフリーのリフォーム』なども考えておいた方がより具体的な数字にはなりますが、今回はあくまで簡単な目安としてご覧ください。
優先順位を明確にする
ではここまでで4つのリスクと、具体的な6つの心配をあげました。
この6つの不安要素に関しては、どれも保険で補てんすることができます。
心配に対応する保険は、それぞれこんな感じです。
| 心配 | 対応できる保険種類 |
|---|---|
| 万一の葬祭費用 | 生命保険 |
| 遺族の生活費 | 生命保険、収入保障保険 |
| 傷病による医療費の出費 | 医療保険、がん保険 |
| 傷病による収入減少 | 医療保険、就業不能保険 |
| 教育費の不足 | 学資保険、外貨建保険 |
| 老後資金の不足 | 個人年金保険 |
それぞれの保険種類について概要が知りたいという方は、是非こちらから確認してみて下さい。
ただ、これらすべての保険に加入して準備する、というのは保険料の事を考えると現実的ではありません。
どのリスクが一番心配か、起こってしまった場合に生活が困窮するか・・・という視点で優先順位をつけていきましょう。
たとえば『お葬式は金額を抑えてもできる。遺族の生活費としてなら収入保障保険で準備できるから、生命保険はあんまり大きい額はいらない。収入保障保険の優先度は高め』『入院手術は出費増、収入減のどちらのダメージもあるから医療保険の優先度は高め』といった感じです。
ぜひ、ここはご夫婦で現在の預貯金額も含めてお話ししてみて下さい。
現在の加入保険の内容を吟味する
すでに保険に加入している場合は、改めて考えた優先順位にもとづいて内容を確認してみましょう。
保険証券や、年に1度送られてくる契約内容のお知らせといった書類で、加入している保険の内容は確認できます。また、検討時に使った商品パンフレットなんかもあると確認がしやすいと思います。
必要な保障内容が準備できているなら、わざわざ入りなおさなくともOK。
今より若い時に加入した保険ですから、そのまま継続したほうが保険料も安く続けていけるはずです!
また、「大体はいいんだけど、この保障はいらないな…」という部分があった場合、該当箇所によってはそこだけを解約し、保障を削って保険料も安くできる可能性があります。その時は加入先の保険会社、もしくは代理店に一度連絡してみて下さい。
保険は一度解約してしまうと戻せないので、後悔することがないように確認をしましょう!
もし一人で確認するのが難しいという場合は、保険のプロに保険内容の確認をしてもらえる無料相談サービスを利用するのもおすすめです。
無料相談サービスはこちらから→『保険無料相談.com』
ここまでの内容を踏まえて、後は新規で加入する保険についてリストアップをしましょう。
先ほどもお伝えしましたが、全てのリスクに保険で備えるのは保険料が大きくなりすぎますので
・発生した場合に金銭的な負担が大きなリスク
・生活が立ち行かなく可能性が高いリスク
つまり、家族の生活を守るために必要な保険を優先的に用意していくのがおすすめです。
家族を守るための保険
ここまででは、保険を考えるためにはどこから考えればいいか、どんなリスクに備えるべきなのか、という材料集めについて主にご紹介させていただきました。
では次に、家族の生活を守るため・・・という観点から、いくつか保険の内容についてご紹介ご説明していきたいと思います。
世帯主が亡くなった場合の生活を守る保険

このリスクには、表でご紹介したように以下の2つの保険で対応できます。
・生命保険
・収入保障保険
【生命保険】
生命保険は、被験者が亡くなった場合に保険金が支払われる保険です。
保険期間中であれば、いつ亡くなっても契約時に設定した保険金額が支払われるので『この額は必ず残してあげたい』という時におすすめです。
保険期間は一生涯か、一定期間か、希望に合わせて選ぶことができます。
例えば、リスクのご紹介の中に下記の葬祭費用の目安を『火葬のみで約20万円、家族葬で約60万円、一般葬で100万円以上』とご紹介していましたが、自分の葬儀費用は保険で残しておきたいと考えるならば、生きている間に保険期間が終わっては困るので保険期間が一生涯の生命保険が適しています。
また、子どもが小さいうちにもしもの事があったら、教育費も生活費も抱える家族が心配だ・・・という場合は、子どもが18歳になるまで、22歳になるまでといった期間限定の保障が得られる定期保険が適しています。
備えるべき目的を明確して、適正な保険料、適正な保障を得るようにしましょう。
具体的な商品が知りたい方、資料が欲しい方はコチラへどうぞ。
→生命保険の請求はこちらから
【収入保障保険】
収入保障保険は、被験者が亡くなった場合に保険金が支払われる保険という意味では生命保険と同じですが、違うのはその保険金の受取方です。
生命保険は保険金が一度に全額支払われるのに対して、収入保障保険は契約時に定めた金額が、保険期間中毎月支払われるというお給料のような受取方が基本です。
そのため、収入保障保険は総額いくら受け取れるか?というのは確定されておらず、万が一の際には月15万円受け取れるという契約の場合だと、受け取れる総額は下記のようになります。
▶保険期間残り10年で亡くなった場合
15万円 × 12ヶ月 × 10年 = 1,800万円
▶保険期間残り5年で亡くなった場合
15万円 × 12ヶ月 × 5年 = 900万円
メリットは、受取金額が常に一定額でない分、生命保険と比べ保険料が割安に備えられる点と、お給料がわりとして毎月の生活費の補てんで使いやすい点です。
子どもが独り立ちするまで、配偶者が年金をもらいだすまでなど、必要な期間を設定して効率的な準備を行いましょう。
具体的な商品が知りたい方、資料が欲しい方はコチラへどうぞ。
→収入保障保険の資料はこちらから
世帯主が働けなくなった場合の生活を守る保険

このリスクには、表でご紹介したように以下の2つの保険で対応できます。
・医療保険
・がん保険
【医療保険】
医療保険は、病気・ケガで入院や手術などを行ったときに給付金が支払われる保険です。
最も基本的な保障内容としては、『入院1日○○円』、『手術は程度や入院の有無により異なる額の保障がされる』といったものです。
ただ、最近では『入院した時点で一時金保障が受け取れる』といった保障や、『手術の保障を省いて保険料を抑えられる』といった内容など、多様な展開を見せるようになってきています。
シンプルな入院給付金、手術給付金で準備できるものであれば『2.2お金を見える化する』の項目でお伝えしたように、入院給付金は入院1日1万~1.5万円の保障プランを1つの目安に検討いただければと思います。
また、入院した時点で受取れる一時金の保障がある保険であれば、使い道自由のまとまったお金を手にすることができます。
治療費に充てるのはもちろんの事、収入減少の補てんに充てることも可能なので利便性は高いと言えます。
具体的な商品が知りたい方、資料が欲しい方はコチラへどうぞ。
→医療保険の資料請求はこちらから
【がん保険】
がん保険は、医療保険とは違いがん治療に対する保障に特化した保険です。
がんは高額な治療を用いることもあり、治療期間が長引き医療費が高額になりがちである・・・という事から、特に手厚く保障が欲しい方におすすめの内容です。
入院は無制限で日額〇円保障、放射線や抗がん剤治療などを治療別で保障を用意、診断時には一時金・・・といった内容のものが多く、金銭面で安心してがん治療を行えるようにといった充実の内容になっています。
ただし、もし現時点で月々保険料に回せる金額に余裕がない・・・という場合であれば、がん保険の優先度は下げてもいいかもしれません。
というのも、繰り返しになりますが、がん保険はがん治療に対する保障に特化した保険だから。
医療保険であれば、がんでも、がん以外の病気、けがでも、条件に当てはまれば使うことができますので、限られた金額の中でどちらかを選ぶのであれば個人的には医療保険をおススメします。
もちろん『がんに対する不安が強い』『がん以外の治療であれば預貯金で十分に対応できる』という場合はその限りではありませんので、要望に合わせてご判断ください。
具体的な商品が知りたい方、資料が欲しい方はコチラへどうぞ。
→がん保険の資料請求はこちらから
子供の教育費を準備するための保険

最後に、教育費準備のための保険では、表で上げた下記2つの保険をご紹介させていただきます。
・学資保険
・外貨建て保険
【学資保険】
子育てで必要になるお金に焦点を当てた保険の種類ですが、注意したいのは貯蓄性重視タイプと、保障重視タイプの二種類の保険がある、という点です。
一般的に学資保険という時には貯蓄型重視の内容。
こども保険という時には保障重視の内容になっていることが多いです。
選び方のポイントとしては、自分がよりどちらを備えたいかを明確にすること!
シンプルに学費にあてられるお金を準備する目的で、払った以上に受け取れるようにしたいなら貯蓄性重視の学資保険がおすすめ。
契約者(原則は両親のどちらか)に万が一のことがあった時や、子どもの医療費にも準備することを第一としたい。教育費費用にあてられる保障は第二でいいので準備したい。という場合は保障重視の子ども保険がおすすめです。
また、どちらにも共通して準備できる「教育費にあてられる保障」については、商品によりお祝金を受け取れる回数・タイミングは異なりますので、注意が必要です。
また、貯蓄性重視の学資保険ではどのくらい増えるのか。保障重視のこども保険ではどんな保障が準備できるのかも異なりますので、方向性を定めたらしっかり比較検討を行いましょう。
具体的な商品が知りたい方、資料が欲しい方はコチラへどうぞ。
→学資保険、こども保険の資料請求はこちらから
【外貨建て保険】
外貨建て保険はその名の通り、日本円ではなく米ドルや豪ドルといった外貨で保険料を支払い、運用し、受け取る保険の事を言います。
そのため、「外貨建て保険」といった場合は医療保険や生命保険といった『目的』での名称ではないので、その機能は生命保険だったり個人年金保険だったりと様々です。
この保険の特徴としてはこんなところあげられます。
・日本円より利率が高い外貨を活用する為保険の運用がしやすく、保障に対して割安な保険料で準備できる。
・円高、円安の影響により、受取時に為替差損、為替差益が発生する可能性がある
・外貨を活用するためにかかる特有のコストがある
つまりすごく簡単にいうと、払った保険料以上に受け取れる可能性もあれば、為替の動きによっては期待した額が日本円で受取れない可能性もある、という事。
これだけ聞くと「大丈夫なのかな?」と不安を感じると思いますが、しっかり仕組みを理解していただければ「絶対なし!」な商品ではないことが理解いただけると思います。
外貨建て保険はその特性上、直接説明を受けて申し込む対面販売専用の商品になっていますので、ぜひ最初から選択肢から外すのではなく、一度説明を聞いてみていただきたいと思います。
具体的な商品が知りたい方、資料が欲しい方はコチラへどうぞ。
→外貨建て保険も資料請求できるページはこちら
一度、直接説明を聞いてみたい方はコチラへどうぞ。
→無料の対面相談サービスの申込みができるサイトはこちら
最後に
今回は、結婚などで生活環境が変わる時にぜひ考えていただきたい内容についてご紹介をしていきました。
ひじょうに長くなってしまったので、最後に内容をざっとおさらいしておきたいと思います。
【例】
・仕事、働き方はどうするか?
・子どもは欲しいか?教育方針は?
・賃貸か持ち家か?
・お金に関して現在状況はどうなっているか?
どの項目にも関係してくるのは、生活とは切り離せない『お金』の事です。
なかなかデリケートで話しづらい事だからこそ、最初にしっかりとお話しいただくことをおすすめします。
②保険の検討・見直しをしよう
考える順番としてはこの流れです。
・リスクを考える
・お金を見える化する・優先順位を明確にする
・(既加入保険があるなら)現在の加入保険の内容を吟味する
特に、リスクを考えるスタートが大事ですが、一般的にはこんなリスクが考えられます。
【例】
●配偶者の死亡
→葬祭費用
→遺族の生活費
●自身、配偶者の病気、けが
→医療費の出費
→収入減少
●教育費の不足
●老後資金の不足
③最優先事項は『家族を守ること』
リスクは様々ありますが全部に完璧に備えることは難しいです。
家族を守ることに直結する保険の検討を最優先にしましょう。
ちなみに、リスクに対応できる保険一覧はコチラでした。
| 心配 | 対応できる保険種類 |
|---|---|
| 万一の葬祭費用 | 生命保険 |
| 遺族の生活費 | 生命保険、収入保障保険 |
| 傷病による医療費の出費 | 医療保険、がん保険 |
| 傷病による収入減少 | 医療保険、就業不能保険 |
| 教育費の不足 | 学資保険、外貨建保険 |
| 老後資金の不足 | 個人年金保険 |
通してお伝えしたいことは、『何となく準備するのではなくて、適切に無理なく無駄なく備えましょう』ということです。
それぞれの家庭によって心配もリスクも違えば、適した準備の方法も違います。
今回、計算などの例も挙げましたが、是非ご自身たちの場合はどうなのか?ということをしっかり考えてみてください!
とはいえ、それもシンドイしそんな時間も気力もない・・・という方もいらっしゃると思うので、そんな時はプロに相談してしまうのは有効な手段です!
自分で悩むより早く・確実に問題点を洗い出してくれ、解決策となる提案までしてくれますよ。
方法の一つとして、是非ご検討ください!